では、さっそく!
個別指導をしていると、生徒一人ひとりの“基準”が見えてくる。
「昨日は5時間も勉強しました!」と自信たっぷりな子もいれば、
「昨日は5時間しか…」と反省する子もいる。
同じ「5時間」でも、その意味は天と地違う。
・前者は「やりきった」という自己満足。
・後者は「まだ足りない」という危機感。
この捉え方こそが、伸びるか否かの分かれ道だ。
「勉強時間」が問題ではなく、その時間を、
・どんな基準で評価しているか?
・どういう思考や行動で生きてるのか?
これが問題なんだ。
例えば、山登り。
近所の丘に登って「よし!登ったぞー!」と大喜びする小学生がいる。
一方で、標高8000メートルの頂に酸素ボンベ背負って挑むプロクライマーがいる。
どちらも「登った」この表現自体は使える。
ただ、それが示す言葉の重みは全然違う。
勉強もこれ同じで、
「やった」と心底思える基準。
このレベルによって、かかる負荷も密度も、結果の出方も変わってくる。
結局、
学年で100番の生徒は、100番なりの基準で物事を見ているし、
学年で1番の生徒は、例外なく、1番の基準で毎日を生きている。
前者は、「このくらいやれば十分」
そう感じるラインが100番目相応にある。
一方で、後者は、それが1番相応にあるし、
「1番のフィルターですべてを見ている」
というか、1番になる原因しかないから、結果も1番にしかならないわけだ。
一番1番にふさわしい思考と行動をしているから1番なわけだ。
同じ“頑張った”でも、「当たり前の基準」が違えば、
その中身や得られる対価は、花火と火花くらいの差になる。
これがまず伝えたいこと1つめ。
基準を上げる方法は以下に書いています。
基準は「環境」によっても決まる
2つめ。人間の能力は、
「①投資額✕②自己努力」
基本的には、上記で決まる。
①のレベルが10、②が80なら、
「10✕80=800」だし、
①のレベルが80、②が30なら、
「80✕30=2400」になる。
以上が前提で1つ、現実の話をしよう。
あんまりこういう話したくないけど、
面白いデータがある。
・東京都の中学生で、塾にかける費用は、「年間25〜35万ほど」これが平均値。
・MARCH以上を目指す家庭なら、「年間80〜100ほど」これが平均値。
もちろん、
投資すれば伸びる
っていう単純な話じゃないけど、
このデータが教えてくれるのは、先に挙げた掛け算の公式①において、
「登る山に対する最低条件がある」
という事実だ。
当然②においてもあるわけだから、
それぞれの基準をクリアして初めて、
「登りたい山の頂に到達する可能性が生まれる」ということだ。
そして、小学生、いや、もっと前からの投資も加味すると、
その差は年齢が上がるにつれ、倍々で広がっていく。
もう1つ、ある私立大学医学部の話をしたい。
これは知り合いの医者本人から直接聞いた話だけど、、、
やっぱやめた!!笑
さすがにブログで暴露はまずそうだから会った人限定で話そう。
マジで衝撃だから会った時に聞いてね。
結局、
「自己(教育)投資」ってさ、実は人生で1番リターンが大きいんだよね。
これは、OECD(国際的な調査機関)のデータでも証明されてるけど、
「教育に投資した人は生涯所得がグッと上がる」ってね。
例えば、
・高卒と大卒なら、生涯年収で、数千万円〜1億変わるし、
・大卒で、上場企業と非上場なら、さらに1億変わってくるというデータもある。
つまり、
「投資すればするほど将来的なリターンは大きくなる」
ということ。
だから、社会人には特に伝えたいけど、
「自己投資しない=自分の可能性を狭めてる」
ってわけだし、
「自己投資する=自分の可能性を広げている」
って構図になる。
身も蓋もない話だけど、例えば、
A君(年間100投資)→頻度の高い指導やマネジメントで基準を押し上げられ続ける。
B君(年間50投資)→自己管理の比重が高まる。
投資の差は、「努力の質」の差になるってこと。
つまり、“どれだけ頑張ったか”ではなく、
“どれだけ正しい基準で頑張れたか”
これが未来を分けるということだ。
「平均的な投資なら、平均的な結果しか生まれない」
例えば、学校の成績なら、理論上、
100人いれば50くらいの立ち位置に近似して因果応報だし、
「得たい結果があるならそれ相応の犠牲と代償が絶対条件」で、
この話は当たり前すぎるほど当たり前な話だけど、
実際行動ベースで、社会人含めて、投資以外にも色んな面で、
どれだけの人間がアプローチできてんのかなとも思うよ。


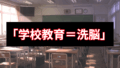

コメント