例えば、
1、ヘラヘラ笑ってごまかす
2、悔しそうな顔をする
3、無言で答案をしまう
4、落ち込む
などなど・・・
ここで、はっきり言っておきたい。
1は論外。
2は可能性の塊。
3と4は背景による。
まず、3について。
これは2種類あって、
まず、背景に「ドライに自分を見てる」なら、むしろ1番可能性を秘めている。
結果に対して、いい意味でドライ。
つまり、感情論ではなくロジカルに自己分析する。
こうやって自分を客観視できる人間はポテンシャルが高い。
次に、何も感ない。このタイプなら、1より論外。
そして、4。
落ち込むこと自体は、何も悪くない。
情けない、恥ずかしい、無気力になる。
そんな状態が出てくるのは、むしろ“戦った証拠”だ。
そして、俺達はロボットじゃない。人間だ。
とんでもない額を稼いでる大社長でも、
世界的に有名な圧倒的スーパースターでも、
彼らでも、落ち込むことは絶対にあるし、
俺も入試に落ちた時は1日中家で絶望に浸ったし、
今までの人生で何度絶望で肩を落としたかわからない。
みんな、あなたと同じ”感情の生き物”なんだ。
「みんな落ち込む」
ただ、問題はそのあとだ。
「引きずるかどうか」で未来は変わる。
例えば、テストの結果が悪くて、1週間ずっとダークモード。
ため息1日300回。
帰宅後はベッドで天井の一点を見つめる日々。
そんなA君がいたとする。
一方、同じく結果が悪くて落ち込んでたけど、
1日ですぐに切り替え行動。
2日目からは、問題を見直し、解き直し、同じミスを繰り返さないように動き出しているB君。
彼はもう次の戦がスタートしている。
さて、次のテストで結果を出すのはどっちだろう?
もう言うまでもない。
この時点で次のテストの結果は決まってる。
点数そのものより、その点数をどう受け止め、どう動いたか?
その「メンタルスキル」。そして、「アクション」
この2つにしか、未来の伸びしろは存在しない。
ここまでまとめると、
・ヘラヘラ、悪い意味で何も感じないスラリヒョンは論外
・冷静に結果を受け止め省みるドライタイプは可能性の塊
・落ち込んだあとすぐ立ち直るタイプも可能性の塊
・落ち込み続けるタイプはメンタルスキルを上げろ
落ち込むのは“止まる理由”じゃなくて“自分と向き合うキッカケ”
よく聞かれる。
「どうしたら、(勉強や人間関係で)落ち込まないようになれますか?」と。
俺の答えは、「落ち込まないようにする必要なんてない」ってこと。
必要なのは、「落ち込んでも動ける力」だ。
そのためには、
・失敗を“次への好材料”に変える
・点数で“自分の価値”を決めない
・間違いを“伸びしろ”として受け取る
例えば、俺が今の思考で失敗した時どう捉えるか?
・超ラッキー!失敗した人の痛みがわかった(貴重な経験だな!経験値UP)
・「こうすれば失敗するんだな」ってことがわかった!
・自虐ネタとして今後どこかで使って人を笑わせよう!
などなど・・・
上記は一例だけど、こんな要領で捉えるし、
こういう思考をあなたも育んでいく必要がある。
俺は色んな人間を見てきたけど、
伸びる人間、優秀な人間は、たとえ一時的に負けても、立ち直るのが圧倒的に早い。
勉強に限らず、成長スピードが速い人には共通点がある。
冗談抜きで、このスキルを身につけるだけで人生が170度くらい変わってくる。
「落ち込むな」と言いたいんじゃない。
むしろ落ち込めばいい。
ただ、それを理由に立ち止まるな。引きずるな。
「味わった悔しさ」をいかに温度保ったまま行動に還元できるか?
これが分岐点だ。
長期的に成績が上がる生徒ほど、
失敗した翌日にすでに次の目標を見ている。
気持ちを切り替えるスピードが未来のスピードを決めている。
保護者としてできることもある。
子どもが落ち込んでいたら、励ます必要一切なし。
ただ、「で、次はどこをどう改善する?」そう聞いてあげてほしい。
感情ではなく頭を使ってまた動き出せるように、コーチングスタイルで問いを投げる。これだけでよい。
テストは終わった瞬間から、もう次が始まっている。
その現実に早く向き合えた者から、変わっていく。
だからこそ、一時的に落ち込むのはかまわない。
でも、引きずることだけはやめておこう。
未来は、いつだって次の一歩からしかつくられない。
「リバウンドメンタル」
「立ち直るスピードを上げる」
圧倒的ポジティブ人間になる方法は以下に書いています。



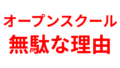
コメント